公務員から公務員に転職すれば、きっと今より働きやすくなるはず。
そう思って別の自治体に転職したものの、実際には「想像と違った」と後悔してしまう人も中にはいます……
公務員からの転職を悔いのないものにするためにも、ここでは、実際に筆者の周囲で公務員から公務員に転職した4人の体験談を紹介するとともに、転職のデメリット・後悔する人の共通点を詳しくご紹介します!
- 公務員から公務員に転職できる?
- 転職したら給与・退職金は減る?
- 別の自治体に転職して後悔する人の共通点は?
- 公務員から公務員の転職活動はバレる?
この記事を書いた人

あつし
8年間勤めた公務員を辞めてIT企業に転職したアラサー。今はフリーランスライターとして3つの転職メディアで活動中。元エンジニア・元消防士。Webライター歴4年。(詳しいプロフィールへ→)
公務員から公務員に転職はできる?
公務員から公務員への転職はまったく問題なく可能です。実際に僕のまわりでも、市役所から市役所、警察官から学校事務など、同じ公務員の世界で転職した人は何人もいました。
転職の理由も「地元に戻りたい」「もっと自分に合った仕事がしたい」などさまざま。公務員間の転職には法的な制限もなく、採用試験に合格すればOKです。
とはいえ、転職理由が弱かったり、前職を短期間で辞めていたりすると不利になることもあるので、しっかり対策して臨む必要があります。
転職方法は「通常採用」と「経験者採用」の2パターン
公務員から公務員への転職ルートは大きく分けて2つあります。
ひとつ目は「通常採用枠」での再受験。主に20代が対象で、年齢制限を満たしていれば、新卒と同じように筆記・面接試験を受けて採用されます。
もうひとつは「経験者採用枠」での転職。こちらは社会人経験や公務員経験を活かせる制度で、30代や40代でもチャンスがあります。
とくに最近は経験者枠の募集も増えていて、即戦力として歓迎されるケースも多いです。それぞれの特徴を理解し、自分の年齢や経験に沿って選ぶことが大切ですね。
よくある転職ルート(市→県、県→国、国→市 など)
公務員間の転職では、よく見られるルートがあります。
たとえば「市役所から県庁」はキャリアアップを目指す人に多く、「国家公務員から市役所」は地元に戻って家庭とのバランスを取りたい人によくあるパターンです。
逆に「地方から国家」へ挑戦する人もいて、その場合はハードルがやや高め。地方公務員として働きながら、試験対策に長期間取り組んでいるケースが多いです。
公務員間の転職は、目的やライフスタイルによって変わってきます。
筆者の身近で公務員から公務員に転職した例【体験談】
僕のまわりには、公務員から別の公務員に転職した人がけっこういます。
この項目では、実際に身近であった「4つの転職例」と、そこから見えてきた共通点を紹介します。
転職例① 市役所から市役所
学生時代の後輩は、地元の市役所から別の市役所(同県)に転職しました。
転職の理由は「結婚」で、奥さんの実家近くに引っ越すことになったのがきっかけ。パートナーの地元で働くため、転職を決意したそうです。
試験対策は仕事の合間にコツコツ続けていたみたいです。
ちなみに、その人の父親は地元の市議会議員で、他の自治体と強いコネクションを持っていたというウワサも……
見えない力が働いたのかどうかは、ご想像にお任せします。。。
(僕はコネだと思います。笑)
転職例② 消防士から村役場
これは僕の先輩のケースで、配属希望を出していた部署「予防課(消防事務)」に全く異動できずにいたため、転職を決意したそうです。
消防署では、全体の約7割が現場対応の仕事。先輩は「ずっと予防事務の仕事がしたかった」と話していました。
仕事を続けながら約1年間、土日にひたすら試験勉強をしていたとのこと。年齢制限ぎりぎりのタイミングで無事に合格しました。
転職例③ 警察官から学校事務
友人の奥さんは元警察官で、20代の頃に中学校の学校事務職に転職しました。
警察の現場仕事が肌に合わず、精神的に限界を感じていたようで、「もっと落ち着いた環境で働きたい」と思い転職を決意したそうです。
転職例④ 自衛官から消防士
最後は僕の友人のケースです。地元で働きたいという思いから、自衛官を辞めて地元の消防局を志願しました。
1度目の試験は残念ながら不合格。それでも諦めず、2度目の挑戦で見事内定。
「自衛官は転職活動がしづらい」と言われるのは本当らしく、試験を受けるための休暇を取るのも大変だったそうです。
とはいえ、転職活動のために現職を辞めてしまうと、先行き不透明の状態で毎日過ごさなければなりません。
精神的な余裕を保つためにも、現職はできるだけ辞めない方が安全ですね。
【年代別】公務員から公務員の転職で変わる給与・退職金・待遇
公務員から公務員へ転職するとき、年代によって受けられる待遇や加算内容が大きく異なります。
ここでは20代・30代・40代以降に分けて、それぞれの注意点を解説していきます。
20代:職歴加算で基本給が上がる可能性あり
20代での公務員から公務員への転職は、もっとも柔軟性が高く、待遇面でも有利になることが多いです。
とくに注目したいのが「職歴加算」という制度。前職での勤務年数がしっかり加算されれば、転職先でも基本給が上乗せされる可能性があります。
ただし、加算の仕方は自治体によってまちまちなので、事前にしっかり調べる必要があります。
30代:転職後の昇給ペースや退職金の影響
30代になると、転職による待遇の変化がよりシビアになります。とくに気になるのが「昇給ペースが下がる」「退職金の減少」ですよね。
たとえば転職によって役職がリセットされると、結果的に昇給スピードが遅くなることもあります。
退職金についても、転職前の勤続年数が通算されないケースがあり、そのまま転職すると想定より少なくなることもあります。
30代から転職を検討する場合は、国が推奨する老後資金・貯蓄対策の「iDeCo」「積立Nisa」を活用して備えることが大切ですね。
40代以降:採用ハードルは高め・待遇も要確認
40代で公務員から別の公務員へ転職するのは、かなりハードルが高くなります。
なぜなら、一般応募では年齢制限で応募できない可能性があり、経験者採用でも「若手に比べて柔軟性がない」と見られるケースがあるからです。
他にも転職後は役職アップに期待できなかったり、年収が下がる懸念があります。
一方で専門的なスキルや資格、マネジメント経験を上手くアピールできれば、現職より給与や待遇が充実している自治体へ転職できる可能性もあります。
勤続年数や退職金の引き継ぎはどうなる?
公務員同士の転職でも、勤続年数や退職金がすべてスムーズに引き継がれるとは限りません。
実際には「同一制度内かどうか」が大きなポイントになります。
たとえば国家公務員から別の国家機関へ移る場合は通算されやすいですが、地方自治体間では制度が異なり、転職前の勤続がリセットされることもあります。
先程の項目でもお伝えしましたが、退職金が減るケースを考慮しつつ、国が推奨する老後資金や貯蓄対策「iDeCo・積立Nisa」を活用すると安心です。
公務員から公務員に転職した人の共通点
先ほど紹介した転職事例を見ると、公務員から公務員に転職した人には共通点がいくつかあります。
- 「今の職場で一生働く」という固定観念を捨てている
- 自己分析をしっかりして、自分の将来像を明確にしている
- 勤務しながらコツコツ試験対策を続けている
- コネがあれば、素直に活用する
公務員はどうしても「一度入ったら定年まで働くのが当たり前」という空気があると思います。
でもそれは、単なる個人の意見に過ぎません。視野を広げて働いている公務員はきっと多いでしょう。
実際に僕も民間に転職してから、同じく元公務員の同期・仕事仲間に3人出会いました。
「転職」という選択肢があるだけで、気持ちがラクになる人も多いはずです。
 あつし
あつし「ムダな飲み会や意味のない研修に時間を使うくらいなら、勇気を出して欠席し、その時間を有効活用する」
この行動を取るだけで、将来の選択肢が一気に広がると思いますよ!
公務員から公務員に転職するメリット
公務員から公務員への転職には、民間企業への転職にはないメリットが存在します。
その具体的な内容は次のとおり。
公務員から公務員に転職するメリット
それぞれ詳しく解説しますね。
① 民間からの転職者に比べてアピールしやすい
採用試験において、民間からの転職者と比べて「公務員経験者」はアピールしやすい傾向があります。
理由はシンプルで、行政の流れや仕組みをある程度理解しているから。面接でも「自治体間の文化の違い」や「前職との共通点・相違点」を具体的に語れるため、採用担当者にとっても即イメージしやすいです。
とくに同じ職種・分野での転職であれば、「育成コストが少なくて済む」「仕事の吸収が早い」といったプラス材料として受け取られるケースも多いですね。
② 公務の仕組みに精通しているため即戦力になりやすい
公務員としての実務経験があると、組織構造や決裁フローなどに最初から理解があるため、転職先でもスムーズに業務に入れます。
とくに大きな組織であればあるほど、内部のルールや文書の扱い方、行政独特の仕事の進め方に慣れているのが武器になるでしょう。
採用側としても「教育コストがかからない人材」として重宝されるのは納得です。
③ 業務理解・ルール慣れしている点が強みになる
公務員の仕事には、独特な用語や進め方、文書ルールが多いですよね。
こうした「お役所仕事」にすでに慣れていることも、公務員から公務員への転職では大きなアドバンテージになります。
これが民間企業出身の方ならゼロから教えなければならないため、その点では“慣れ”という武器はかなり強力です。
公務員から公務員に転職するデメリット
公務員から公務員への転職には、デメリットもいくつかあります。
なかでも大きなデメリットは、役職アップが望めなかったり、転職活動が難航するケースです。
公務員から公務員に転職するデメリット
① 年収や役職が下がる
意外と多いのが「転職したら給料が下がった…」というケース。公務員から公務員に転職すると、前職の役職や年収がそのまま引き継がれるとは限りません。
たとえば主任や係長だった人が、転職先では“平”の扱いになる可能性もあります。
年齢や経験によっては「職歴加算」される場合もありますが、それでも初任給より少し高い程度になるケースが多い印象です。
年収ダウン・役職ダウンはモチベーションにも影響するので、可能な限り情報収集に努める必要があります。
② 志望動機が弱いと選考で不利になる
公務員から公務員への転職では、「なぜ同じ公務員を選ぶのか?」という志望動機が重視されます。
とくに同じ職種・近い業務内容での転職だと、「なぜ応募したのか?」「現職ではダメなのか?」といった突っ込まれ方をされやすいです。
民間からの転職者なら“公務員を目指す理由”を前向きに伝えやすいですが、経験者だと理由が曖昧なままだとマイナス評価につながりがちです。
転職理由をネガティブに捉えられないよう、応募先の地域や自治体への思い・繋がりを上手く訴求する必要がありますね。
③ 転職後の人間関係や評価制度のギャップに注意
転職先の自治体によっては、組織の雰囲気や評価制度がガラッと違うこともあります。
たとえば、以前は仕事ができる人が評価され、出世しやすい職場だったのに、転職先は「派閥文化」「コネ」が根強く根付いていた……なんてことも。
公務員といっても、職場によって文化や空気感はバラバラです。
転職前に「その職場のリアル」をどうにかリサーチしたいところですね。
④ 仕事をしながら試験勉強は想像以上にきつい
公務員試験の受験準備は、思っている以上に体力も気力も使います。とくに在職中に転職を目指す場合、平日はフルタイムで働きながら、夜や休日に試験勉強を進めなければいけません。
消防士から村役場に転職した僕の先輩も「仕事から帰って勉強するのがキツかった」と言っていました。
年齢が上がるほど集中力も落ちてきますし、プライベートとの両立もしんどくなります。試験勉強が必要な転職は、相当の覚悟が必要だと感じました。
公務員から公務員に転職して後悔する人の共通点
「もっと働きやすい職場だと思ってた…」
「転職なんてしなければよかった…」
実は公務員から公務員に転職して後悔している人も一定数います。
ここでは、そのような方々に共通する3つの特徴をご紹介します。
公務員から公務員の転職で後悔する人の共通点
① 転職すればラクになると思っていた
「今の職場が忙しいから、別の自治体に行けば少しは楽になるだろう」
こう思って転職した人の中には、実際には仕事量や雰囲気が大差なかったり、むしろ忙しくなってしまった……というパターンも少なくありません。
「今の仕事が嫌だから」という理由だけで転職すると、その後も同じことで悩んだり、苦痛に感じるケースが多いです。
転職するなら、“どんな環境なら納得して働けそうか?”としっかり考えておくのが大切ですね。
② 年収や役職が下がる覚悟ができていなかった
年齢や前職の自治体によっては、転職後に年収や役職が下がってしまうこともあります。
「今より良くなるはず」と思っていたのに、いざ転職してみたら給料が減っていたり、役職なしの職員にリセットされてしまったり。
職歴加算や昇給ペースの違いなど、待遇面をしっかり調べずに転職すると「こんなはずじゃなかった」となりやすいので注意が必要です。
③ 志望動機が曖昧なまま転職した
転職試験を突破するためには、志望動機の説得力がとても重要です。
「とりあえず違う自治体に行きたい」「今の職場が合わないから」など、転職の理由があいまいなままだと面接試験で見抜かれ、採用が難しくなることが考えられます。
逆に、しっかりと自己分析をして「なぜその自治体なのか?」「どんな仕事がしたいのか?」を言語化できていた人は、転職活動がスムーズに進み、その後も納得して働けるでしょう。



公務員から公務員への転職は、メリットも多いですが「なんとなく」の気持ちで動くと後悔する可能性もあります。
「どんな働き方をしたいのか?」「何を優先したいのか?」とじっくり考えてから転職活動をスタートするのが、失敗しないコツですね。
公務員から公務員に転職する方法
「公務員の採用試験は一度経験しているから大丈夫」と思う方も多いかもしれませんが、新採用と中途採用では、応募ルートが大きく異なります。
ここでは公務員から公務員への転職方法について、4つのパターンを解説します。
公務員から公務員に転職する方法
① 通常の採用枠で再受験する方法
いちばんオーソドックスなのが、“新卒と同じ枠”で再受験する方法になります。
とくに20代の転職者は、このルートを選ぶ人が多いです。
選考フローは新卒組と同じになるため、筆記試験・面接試験もイチからスタート。公務員のアドバンテージを活かせないのはデメリットになるでしょう。
実務経験があっても優遇されるわけではないので、年齢が上がるほど若手との競争になりやすくなります。
② 社会人・経験者枠を活用する方法
最近は多くの自治体で、社会人経験者向けの採用枠が設けられています。「経験者採用枠」と呼ばれるもので、現職の公務員でも応募可能です。
筆記試験のハードルがやや低めに設定されていたり、面接重視だったりと、通常採用よりも実務経験を評価されやすい特徴があります。
年齢制限も30代後半〜40代前半まで幅広く対応しているケースが多いです。
希望する自治体がある方は、経験枠の採用を行っているかどうか調べると、転職活動がスムーズに進むでしょう。
③ 技術職・専門職なら職種別採用枠も
土木・建築・電気・福祉・保健師など、技術系・専門系の職種を希望する場合は「職種別採用枠」があります。
通常の行政職とは違い、専門スキルや資格保持者が応募の前提となるため、倍率が比較的ゆるやかな傾向にあるのも特徴です。
同じ分野で経験を積んでいる人にとっては、非常に有利な枠といえますね。
④ 民間企業を経由してから再度公務員へ戻る人もいる
少し珍しいルートですが、一度民間企業に転職してから再び公務員になる方もいます。
「一度民間企業を経験してみたい」「子育て後に公務員として復帰したい」など、背景は人それぞれ。
中途採用の面接では、こうした“民間経験を公務にどう活かせるか”を語れると、転職活動で強みになることもあります!
公務員から公務員の転職活動はバレる?
公務員から公務員への転職活動は、以下のポイントを押さえれば高確率でバレずに転職活動を進められます。
- 庁舎内では転職活動にまつわる電話・メールは控える
- 転職活動していることは内定が決まるまで口外しない
- 職場のネットワーク(Wi-fi)を使って受験申込ページなどを見ない
ここでは、公務員からの転職をより安全にするための対策・注意点を解説します。
転職活動が職場にバレるケースと回避策
在職中に公務員試験を受けても、現職に100%バレるわけではありません。
ただし、以下のような行動には注意が必要です。
- 平日に有休を取って面接を受ける
- 転職にまつわるメールや電話を職場で見聞きされる
- 転職について相談しているのを同僚や上司にうっかり聞かれる
対策としては、なるべくスマホを職場で開かず、電話・メールの返信は庁舎外で行うことです。
スマホの通知は、ロックを開かなければ内容が分からない設定に変更し、セキュリティを高めると安心です。
在職中に受験・面接を受ける場合の注意点
公務員の転職活動は、どうしても平日の日中に受験や面接が行われがちです。
だからといって「体調不良で休みます」といった不自然な休み方を続けてしまうと、さすがに周囲に怪しまれます。
可能であれば、有給休暇や夏季休暇、代休などを上手く組み合わせましょう。
連続して休まず、受験日だけピンポイントで休むのがおすすめです。
公務員から公務員への転職には、無理のないスケジュール調整に加えて「事前の根回し」も必要ですね。
公務員から公務員の転職でよくある質問
ここでは、公務員から公務員への転職でよくある質問と回答をまとめています。
事前に疑問点を解消し、公務員からの転職を悔いのないものにしてくださいね!
公務員から公務員の転職でよくある質問
公務員1年目で転職は不利?
転職理由をうまく説明できれば、不利に働くどころか「プラス」に働きます。
今は公務員も民間企業も、どの職場も「若い人材」を欲しがっています。
全く同じ能力・経験を持っている人が応募してきたら、当然のように「年齢が若い人」を採用しますよね。
若さは転職の強み。「もっと〇〇の仕事がしたくて転職活動している」「将来は〇〇の仕事に携わりたい」とポジティブな転職理由を説明できれば、公務員1年目の方も十分内定を目指せますよ!
転職しても職歴加算される?
多くの自治体では、前職の公務員経験が「職歴加算」として反映されます。
ただ、加算の有無や割合は自治体ごとに異なる点には注意が必要です。
「同一職種・同一等級内」であれば加算されやすい傾向ですが、異なる職種(例:事務→技術など)の場合は加算されないケースもあります。
気になる方は、採用担当に直接問い合わせて確認しておくと安心です。
公務員から公務員に転職するなら何歳まで?
年齢制限は受験区分によって異なりますが、「経験者採用」や「社会人枠」であれば30代〜40代前半までチャンスがあります。
もちろん年齢が高くなるほど転職のハードルが上がり、志望動機やこれまでの経験の整合性も重要になります。
ただ、決して不可能なことではないため、「即戦力として何ができるか」をうまく伝える意識を持ちましょう。
退職金は引き継げるの?
条件を満たせば、退職金を引き継げます。国家公務員共済や地方公務員共済で一貫して加入していると、通算される可能性が高いです。
ただし共済組合が変わると、その引き継ぎが複雑になる可能性があります。
筆記試験なしで転職できる職種はある?
ごく一部ですが、筆記試験を課さずに書類選考と面接のみで採用する職種もあります。
たとえば医師・看護師・建築士などの専門職、あるいは任期付き職員や会計年度任用職員のようなポジションが該当します。
ただし「正規職員」ではない場合も多いため、雇用条件にはしっかり目を通すことが大切です。
さいごに|公務員からの転職を後悔しないために
公務員からの転職を後悔しないためには、「人生の目標」「自分の価値観」を明らかにすることが大切だと思います。
たとえば、安定を最優先したい人・昔から憧れていた自治体にチャレンジしたい人は、
なるべく早く公務員試験対策に取りかかる
のがベストです。公務員試験には、年齢制限がつきものですからね。
逆に、今の年収に不満がある・やりたい仕事に就きたいという人は、
民間企業・会社員の道にシフトする
という選択がぴったりかもしれません。
転職の決断はどうしても迷ってしまいますが、「今のままでいいのか?」と立ち止まったこと自体が、将来をより良くするための機会になります。
自分の価値観や働き方を見つめ直してみると、5年後、10年後に納得できる選択ができるはずですよ!



僕のように「民間企業に転職して年収を上げたい!」と考えている人は、以下の記事をぜひご覧ください!




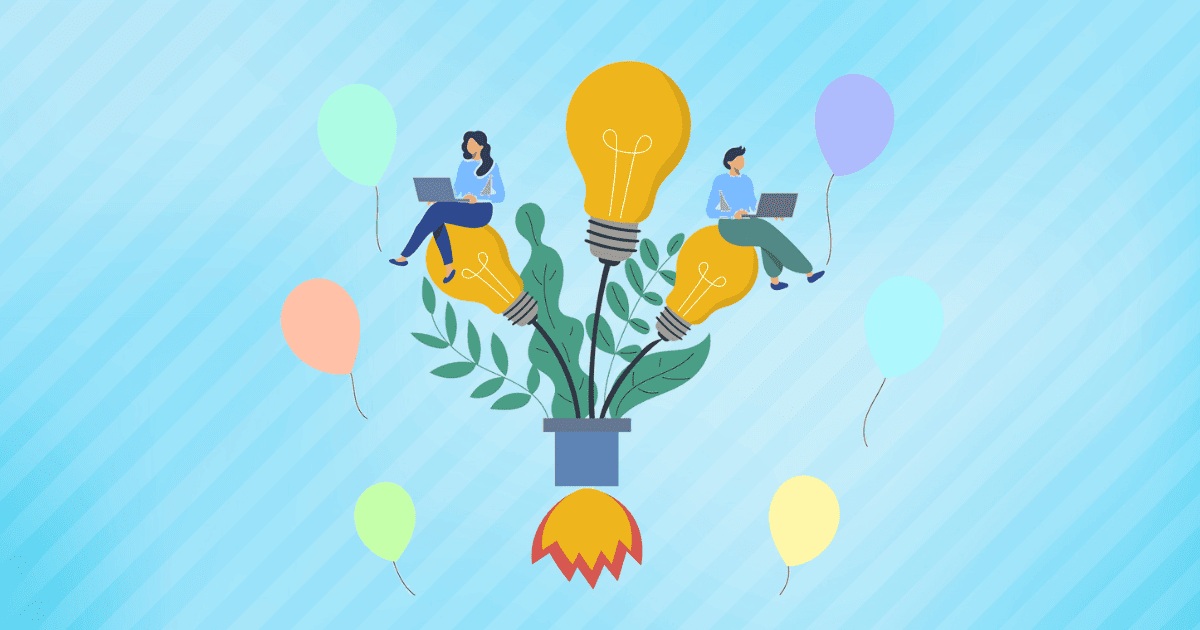
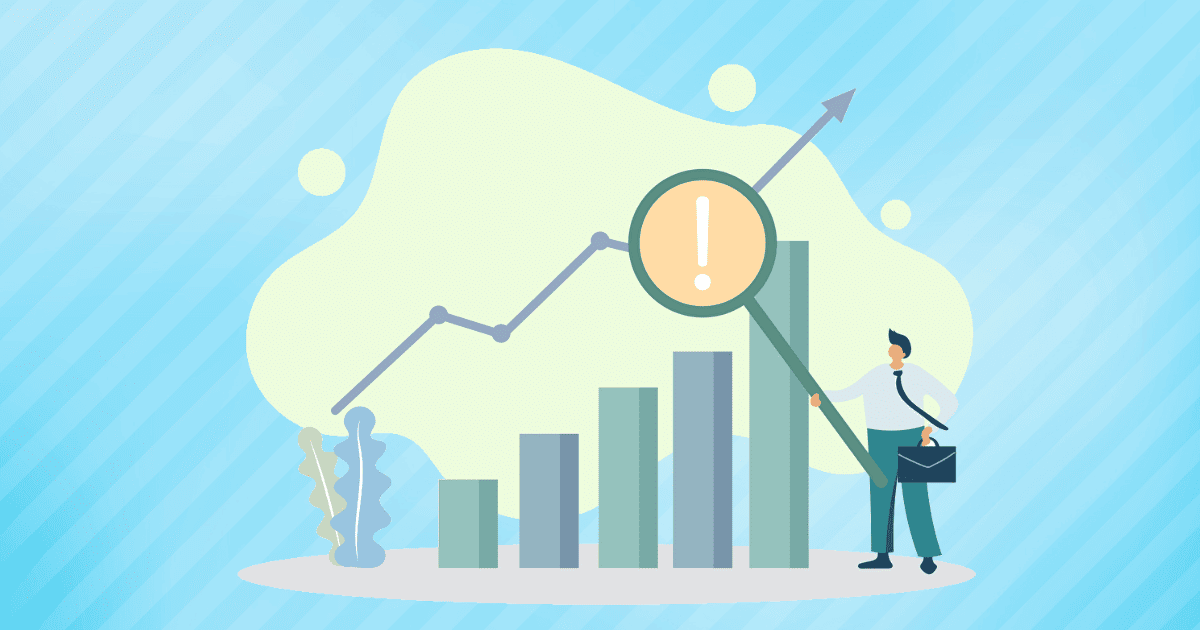



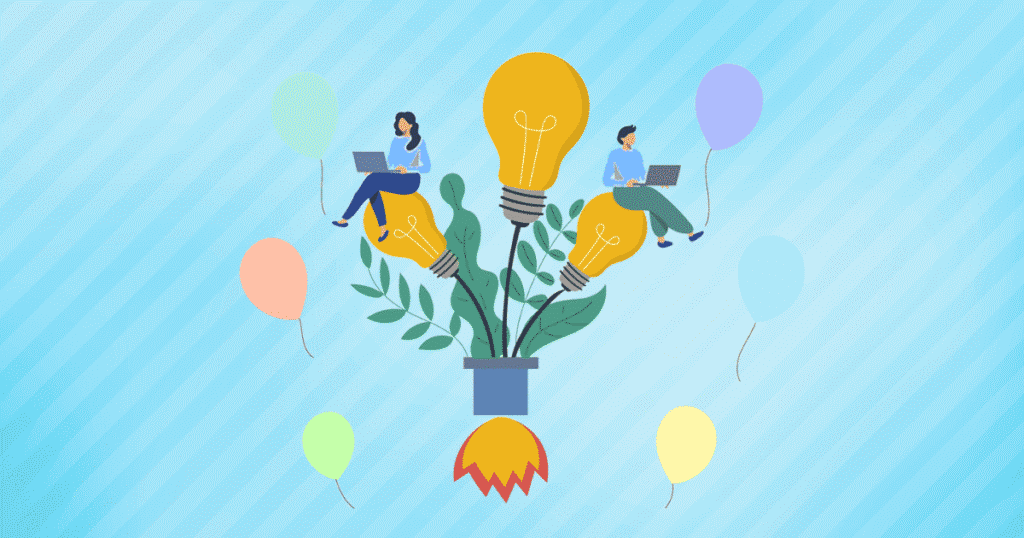
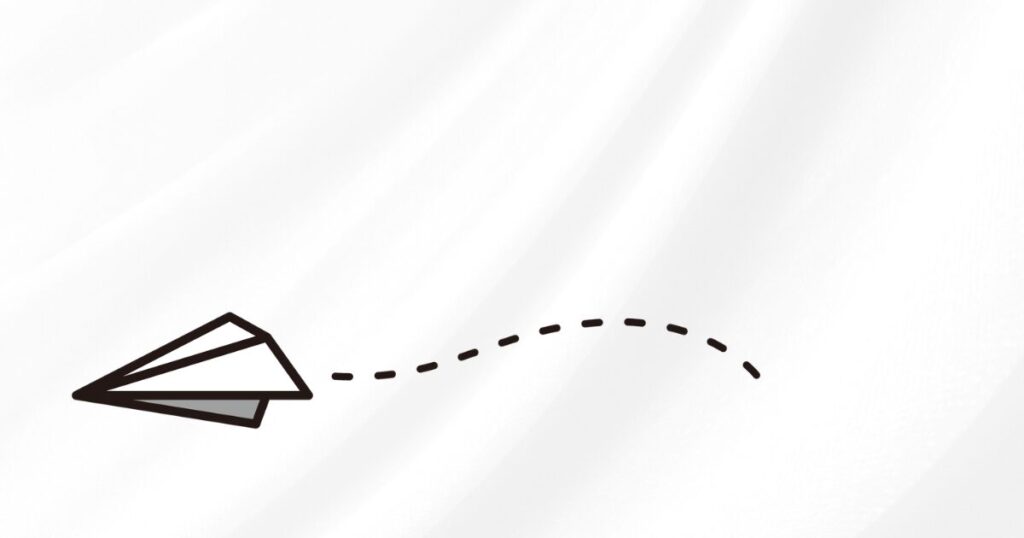


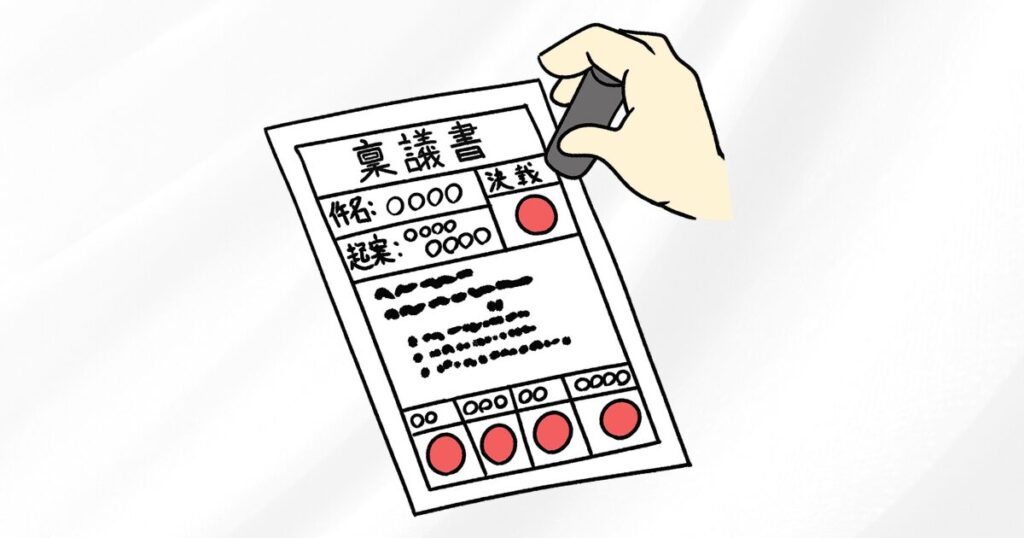
コメント